こんにちは、つみれです。
このたび、イスラエルの歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリさんの『サピエンス全史』(柴田裕之・訳、河出書房新社)を読みました。
世界中の著名人、知識人が絶賛しているという話題の本です。
本作、上下巻となかなかのボリュームですが、内容が非常に濃く、知的好奇心をザクザクと刺激してきます!
人類の壮大な歴史を綴っており、歴史にとどまらず、経済学、心理学、哲学、科学、生物学などなど様々な要素が絡んでくるので、幅広く楽しむことができますよ。
それではさっそく感想を書いていきます。
作品情報
書名:サピエンス全史 文明の構造と人類の幸福
著者:ユヴァル・ノア・ハラリ
出版:河出書房新社 (2016/9/8)
頁数:(上)300ページ、(下)296ページ
スポンサーリンク
目次
人類史を三つの革命という視点から読み解く
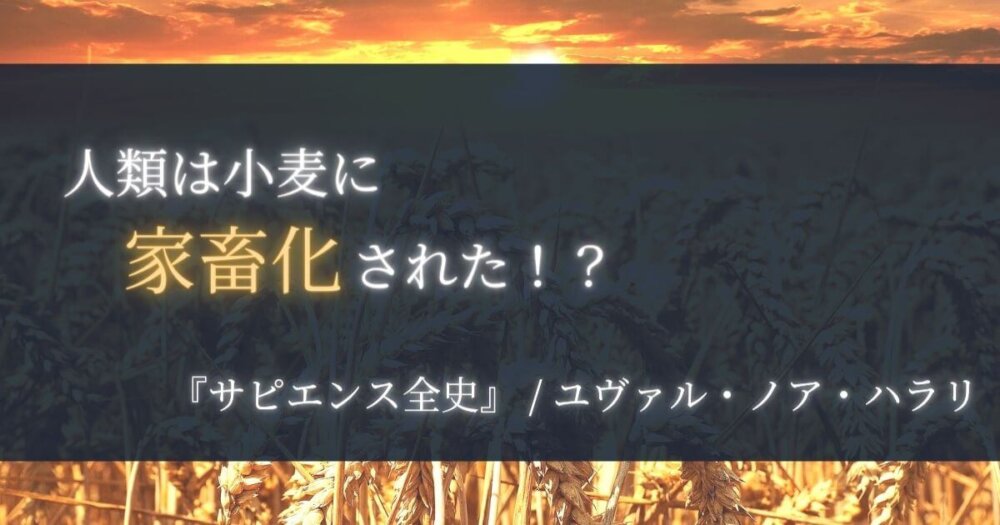
私が読んだ動機
- 読書コミュニティサイト「読書メーター」で評判だった
- アメトーーク!の「読書芸人」企画で取り上げられた
こんな人におすすめ
- 壮大な人類史を味わいたい
- 話題の本が読みたい
- 「幸福とは何か」というテーマについて考えてみたい
「ヒト属」と「ホモ・サピエンス」
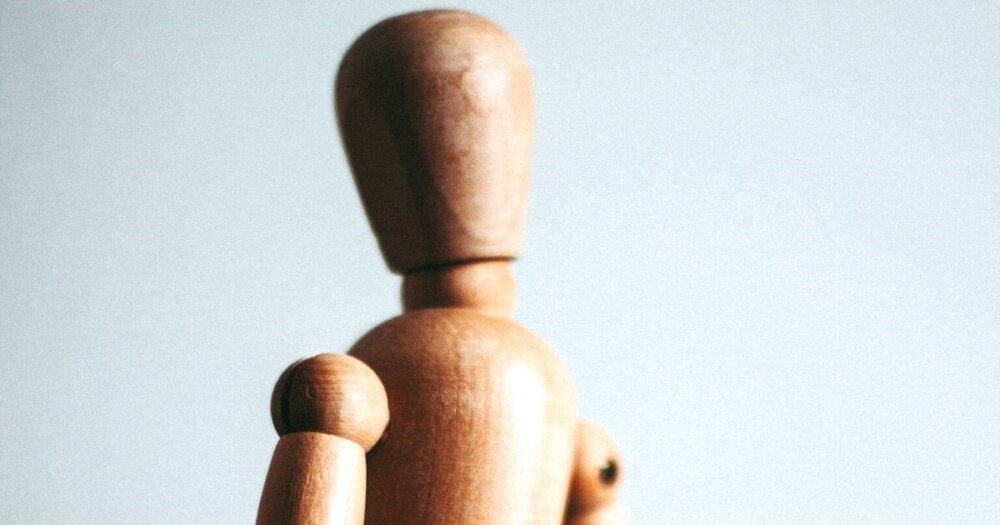
私たちは「人」として生きていますが、実は「ヒト属」というのは、私たち「ホモ・サピエンス」のみを指すわけではありません。
中学生のころ、歴史の授業で習った「ネアンデルタール人」や「ピテカントロプス」なども、分類としては「ヒト属」に位置付けられます。
ところが、はるか昔にホモ・サピエンス以外の「ヒト属」は絶滅してしまったとされています。
では、どうして私たちホモ・サピエンスだけが生きのこり、繁栄しているように見えるのでしょうか?
そして、ホモ・サピエンスはどこに向かおうとしているのでしょうか?
本作はこれらの疑問に対する回答を求め、壮大な人類史を読み解いていく話題の名著です。
いろいろと興味深い考察や新しい視点を提供してくれるので、飽きずに楽しむことができますよ。
人類史を三つの革命で区分

ホモ・サピエンスは、他のあらゆる生物と異なり、食物連鎖の頂点に君臨し、文明を築き上げました。
ユヴァル氏は三つの革命によって、これらが成し遂げられたとしています。
三つの革命とは、下記の通りです。
- 認知革命
- 農業革命
- 科学革命
こうして並べてみてもイメージがつきづらいかもしれませんね。
しかし、実際に読んでみると、目からウロコの挑戦的考察が至るところに現れてきます。
私はなかでも「農業革命」が最高におもしろかったですね。
上巻

上巻はホモ・サピエンスが次第に勢力圏を拡大していった事情の箇所と、「農業革命」に関する分析が最高におもしろかったです。
夢中になって読んでしまいました!
認知革命を成しえた虚構の力

10万年前の地球には、少なくとも6種の人類種が存在したといいます。
しかし、現在では1つの種(つまり、ホモ・サピエンス)しか存在しません。
ホモ・サピエンスだけが生き残り、その後も「繁栄」していった最大のきっかけが「認知革命」だとユヴァル氏はいいます。
認知革命ってなんだろう?
ホモ・サピエンス以外の人類種、そしてその他のすべての生物が持ちえなかった能力があり、それによって認知革命は起こったのです。
この能力こそが、想像のなかにのみ存在する「虚構」というものを発明し、それを信じる力だというんです。
死者の霊や神などの存在はもちろんのこと、国民、お金、人権、法律、正義・・・、全ては人々の頭の中にしか存在しません。
こういったものを信じる力をホモ・サピエンスのみが獲得したとユヴァル氏は述べます。それが今から約7万年ほど前から起こり始めました。
ユヴァル氏は下記のように語ります。
ライオンを見て、「気をつけろ!ライオンだ!」という鳴き声を使って意思を疎通させることができる生物はたくさんいます。
しかし、「ライオンをうまく避けつつ、ライオンが跡を辿っていたバイソンの群れをいついつにどこそこで狩ってやろう」という相談ができるのはホモ・サピエンスだけ。
このホモ・サピエンスの例では、目の前にライオンもバイソンもいないのです。であるのに、それを想像し、信じ、行動を起こせる。
「まったく存在しないものについての情報を伝達する能力」(『サピエンス全史』上p.39)、つまり「虚構を信じる」能力を獲得したことが協力することを可能にしたと言っています。
唯一、生物としてこの能力を獲得することができたからこそ、個体として弱いホモ・サピエンスがネアンデルタール人などの他の屈強なヒト属に勝ったというわけです。
生き残った側の手前勝手な感傷と言ってしまえばそれまでですが、もし、現代に他のヒト属が一種でも生き残っていたら、彼らは私たちの友人だったのか、それとも敵だったのか・・・。
そういうことに思いを馳せてしまいますね。
この後、ホモ・サピエンスは生活圏を広げていくにつれ、現地の生物をつぎつぎと絶滅に追い込んできたという話になっていきます。
ユヴァル氏はホモ・サピエンスを指して「史上最も危険な種」と言い切ります。
現代でも「マグロがいなくなる」「ウナギがいなくなる」などと騒いでいますが、これもこの物語の続編ということになるのかもしれません。
農業革命

本作、この「農業革命」に関するユヴァル氏の考察がおもしろすぎました。
もともと私は農耕の始まりや人間の食性などにも興味があったので、めちゃくちゃおもしろかったです。
私たちが学校で歴史を習うときも、「農耕」は繁栄の象徴として語られることが多かったように思うのですが、ユヴァル氏はこの思い込みに痛打を食らわせてきます。
農耕民の生活レベルは狩猟採集民のものよりも満足度が低く、苦労して労働したほどの見返りを得られていないといいます。
思わず、「えっ!」と思ってしまいますよね。
ホモ・サピエンスは小麦に家畜化された

本書を読んでいて一番衝撃を受けたのがこの箇所です。
犯人は、小麦、稲、ジャガイモなどの一握りの植物種だった。
ホモ・サピエンスがそれらを栽培化したのではなく、逆にホモ・サピエンスがそれらに家畜化されたのだ。『サピエンス全史』上p.107
もともとホモ・サピエンスは、狩猟や採集によって比較的快適な生活を送っていました。
そこには十分な量とはいえないまでも、バラエティに富んだ多様な食料があったのです。
ところがひとたび小麦の戦略によって栽培という手段を習得すると、ホモ・サピエンスは「小麦を世話すること」に人生の大部分を割くようになってしまった、というのです。
「小麦の戦略」っていう表現がいいですよね。
代わりにホモ・サピエンスが得られたのは、大量にあるけれど種類の少ない食料ということになります。
少ない種類の作物に依存しなければならない社会は突発的なトラブルに滅法弱く、干ばつや疫病、虫害などによってたやすく危機的状況に陥ったことは、その後の歴史が証明しています。
また、中学でも習うことですが、畑や家や備蓄可能な食料の存在は「貧富の差」を生み、さまざまな争いを引き起こしました。
結局、ユヴァル氏が言うように、農耕は、ホモ・サピエンスに対し「経済的安心」も「人間同士の暴力から守られるという安心」も与えてくれなかったということになります。
そして、総量が爆発的に増えた食料は、ホモ・サピエンスの総量も増やし、結果的に狩猟採集の社会には戻れなくなってしまいました。
ユヴァル氏はいいます。
農業革命は、史上最大の詐欺だったのだ。『サピエンス全史』上p.107
人類の抵抗

若干、ここからは本の内容から脱線するかもしれませんが、ご容赦ください。
確かに、農業革命に対するユヴァル氏の指摘はもっともですが、最近の健康志向を見ると、人類も一生懸命、小麦の戦略に抵抗しているように見えませんか?
学者は、私たちの脳と心は今日でさえ狩猟採集生活に適応していると主張する。『サピエンス全史』上p.59
例えば、肥満や生活習慣病という現代人特有の健康上の悩みがあります。
もともとホモ・サピエンスは数万年という長い歳月を狩猟採集民として過ごしてきました。
ところが、農耕を習得したことによって短期間のうちに食生活を激変させてしまったのです。
肥満や生活習慣病は、私たちの身体がこの食生活の急変に順応できていないことに対する反応とみることができるわけですね。
小麦の戦略からすれば、ホモ・サピエンスを小麦依存体質にしてしまえば「家畜化」できるということです。
でも、近年、これに抵抗するようなキーワードが登場してきていますよね。
例えば、「糖質制限」であったり、「ケトン体ダイエット」などです。
これらは言い替えると、炭水化物を極力摂らないようにしようということに他なりません。
一世を風靡したバターコーヒーダイエットもこの流れで説明することができます。
まあ、私はうどんとかラーメンが大好きなんですけどね。
スポンサーリンク
下巻

上巻にくらべ、下巻は私の琴線に触れる部分が少なかったのですが、これは私の興味の度合いによるものと思います。
冒頭にも書いた通り、本書は多岐にわたる時代を多彩な切り口で分析しているので、話題がポンポンと切り替わります。
読者にとっておもしろい箇所がまったく異なってくるように思われるのも本書の魅力かもしれませんね。
下巻は基本的に科学革命に関する考察にページの大部分が割かれています。
空白のある地図

下巻の内容のなかでは、特にこの「空白のある地図」の箇所がおもしろかったですね。
近代以前にも世界地図というのは存在したけれど、「よく知らない地域」については、省略したり、空想の怪物で満たしたりされていたといいます。
確かに、海にネッシーみたいな実在不明のよくわからない生物が描かれていたりしますね。
ところが、近代の地図はそれとは様相が異なっているのです。
十五世紀から十六世紀にかけて、ヨーロッパ人は空白の多い世界地図を描き始めた。『サピエンス全史』下p.113
これは、ヨーロッパ人が「無知」を認め、甘んじて受け入れている証だという。
知らないということを知る。これがその後の発展への第一歩だということでしょう。
ここから、コロンブスの新大陸発見のストーリーや、スペインのアステカ帝国征服、インカ帝国征服へと進み、帝国主義と資本主義という話に進んでいきます。
資本主義

私は基本的に資本主義というものを理解しているつもりでいましたが、ユヴァル氏の説明があまりにわかりやすくおもしろかったので、感激してしまいました。
このユヴァル氏という人は、具体例の出し方が本当にうまくて尊敬してしまいます。
店がなければマクドーナッツ夫人はケーキを焼けない。ケーキを焼けなければ、お金を稼げない。お金を稼げなければ、建設業者を雇えない。建設業者を雇えなければ、ベーカリーを開くことはできない。『サピエンス全史』下p.131
人類が何千年もの間はまっていた袋小路が、ユヴァル氏が挙げた上のマクドーナッツ夫人の例です。なんともわかりやすいですね。
近代に入り、この状況を打開する制度がついに発明されました。
つまり、「将来への信頼に基づく想像上の財」(『サピエンス全史』下p.131)、「信用」が生まれたのです。
この実現を可能にしたのが「貨幣」という価値の転換装置だということになります。
つまり、お金を借りて(将来、稼いだお金で返済できるという信用の上に成り立つ)ベーカリーを開くという発明的な選択肢が生まれたことになりますね。
文明は人間を幸福にしたのか

最後にユヴァル氏は「文明は人間を幸福にしたのか」を語り、未来の可能性をいくつか挙げて筆をおいています。
これはいろいろととらえ方があるでしょうから、なかなか判断がむずかしいところではありますが、一つ興味深かったのは、下記の箇所。
歴史書のほとんどは、偉大な思想家の考えや、戦士たちの勇敢さ、聖人たちの慈愛に満ちた行ない、芸術家の創造性に注目する。
(中略)だが彼らは、それらが各人の幸せや苦しみにどのような影響を与えたのかについては、何一つ言及していない『サピエンス全史』下p.240
ユヴァル氏は、人類の歴史理解にとって上記の概念が欠落していると言います。
なるほど・・・。この考え方は、確かになかったかもしれません。
※電子書籍ストアebookjapanへ移動します
終わりに
はっきり言ってしまいますと、著者であるユヴァル氏の頭の回転の速さについていくのに必死で、本書の大部分について私が咀嚼しきれていないという感じです。
いろいろと取っ散らかった感想というか要約になってしまったのは、ひとえに私の力不足ですね。
読む側としての未熟さが際立ってしまいましたが、すばらしい気づきを多く与えてくれる名著だと思います。
冒頭でも触れた通り、実にいろいろな視点から人類史を点検することを試みている作品ですので、「おもしろそうだな」と思った箇所を拾い読みするような読み方もいいかもしれません。
読む人によって、興味深いと思う箇所が全く違うと思いますので、感想なんかを語り合うと白熱すること間違いなしですね。
文庫化したら再読に挑戦してみたい作品です。
最後までお付き合いくださり、ありがとうございます!
つみれ
スポンサーリンク

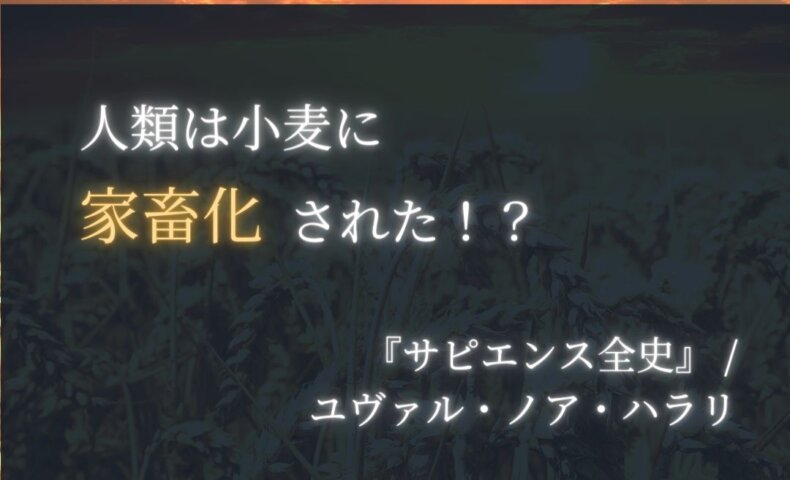


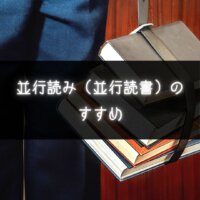
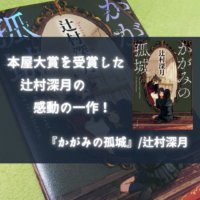


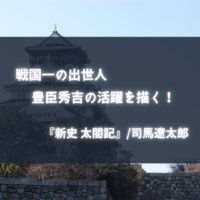
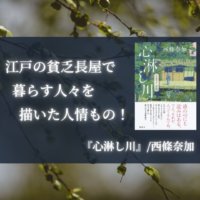
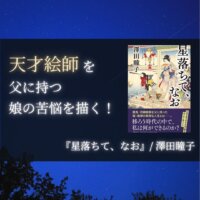


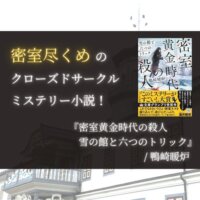
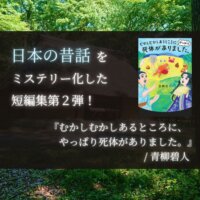
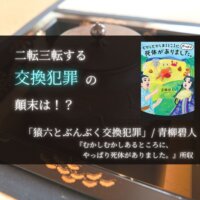
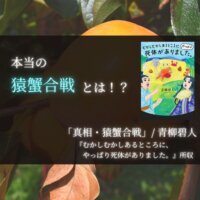
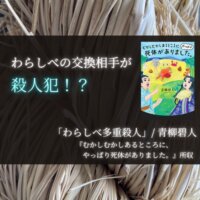
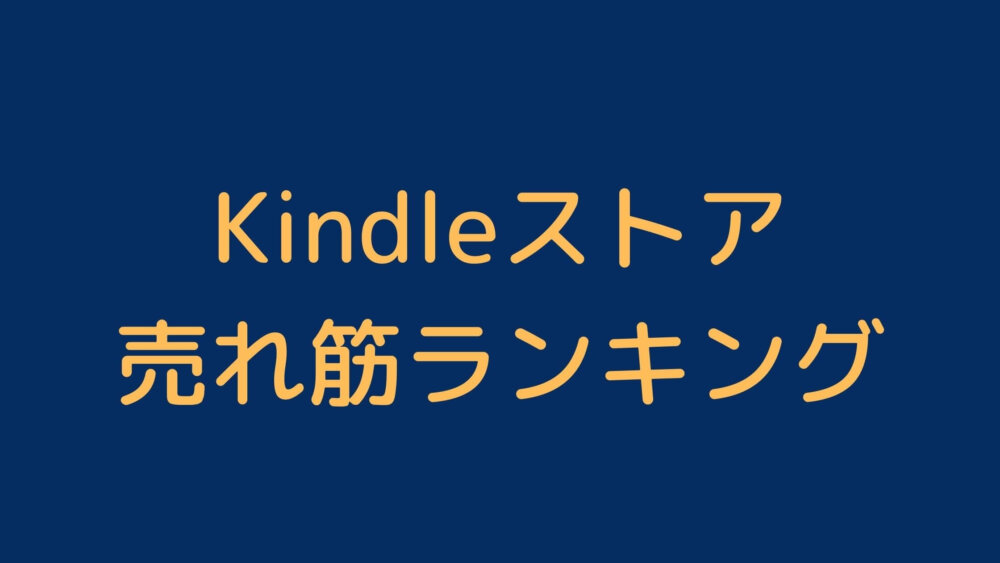

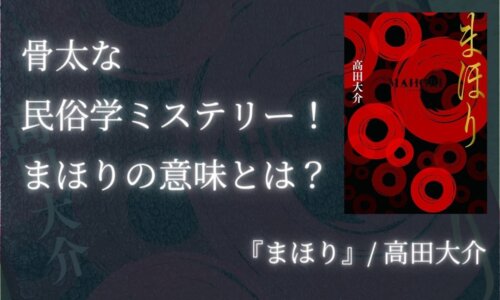
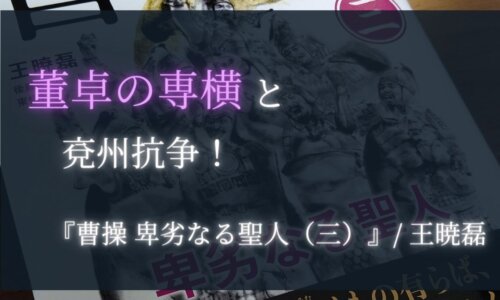
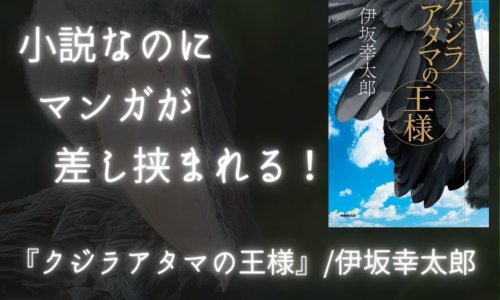
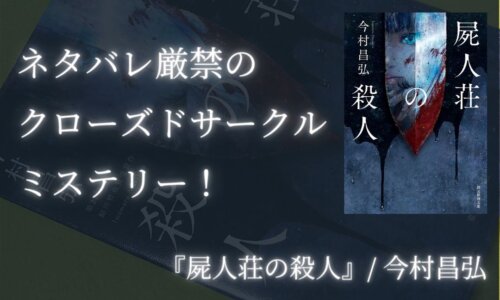
この記事へのコメントはありません。