こんにちは、つみれです。
このたび、円城塔『文字渦』(新潮社)を読みました。
なんかすごい本を読んでしまった気がします。
普段私たちが何気なく使っている「文字」。
この「文字」を使って真面目にふざけまくった実験小説とでも申しましょうか・・・!
とにかく突き抜けた発想の数々に驚かされっぱなしの文字SF(そんなジャンルがあるのか知りませんが)短編集。
それでは、さっそく感想を書いていきます。
※ネタバレ感想は折りたたんでありますので、未読の場合は開かないようご注意くださいね。
※2021年2月16日追記
本作の文庫版が発刊されました。本記事の引用箇所は単行本当時のものです。
作品情報
書名:文字渦
著者:円城塔
出版:新潮社 (2018/7/31)
頁数:302ページ
スポンサーリンク
目次
文字を使った実験小説
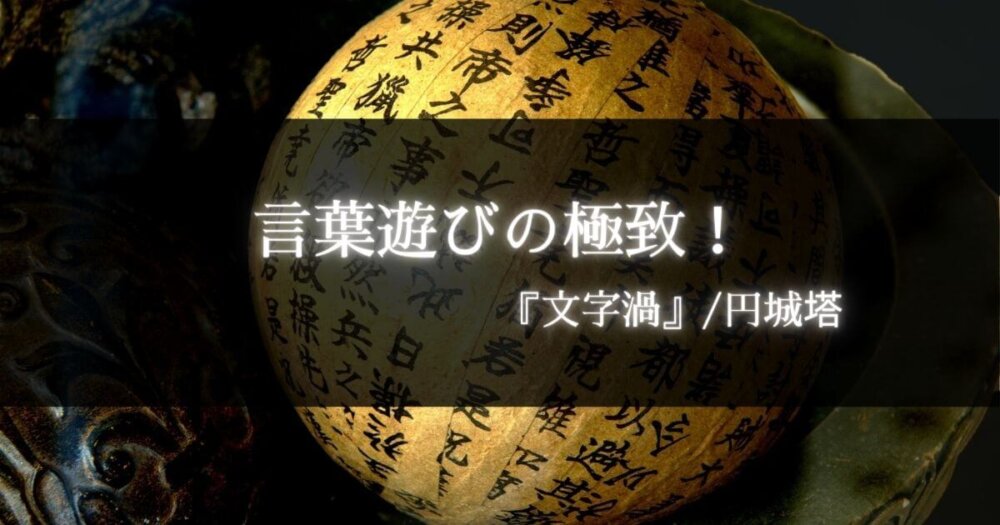
私が読んだ動機
読書会で紹介を受けました。
こういう実験的な本の魅力を短時間で紹介できるのはすごいことだなと読後に思いました。
こんな人におすすめ
- 文字が好き
- 独特の世界観を味わいたい
- 奇抜な発想に驚きたい
とにかく今までに読んだことのない独特の味わいの本でした。
「言葉遊び」といってもいろいろとあると思いますが、この本の「遊び方」「ふざけ方」はちょっと突き抜けています。
この本には短編が全部で12編収録されていまして、1編1編はそんなに分量のあるものではありません。
しかし、なんと全ての編で異なった趣向の文字遊びが展開されています。
なんと、文字が光ったり、闘ったりするんですよ!
君は何を言っているのかね?と思うかもしれませんが、本当にそういう本なんです。
12編の短編のなかにはかなり難解なものもあり、すべてを理解するのはなかなか大変な本です。
かなりクセがあるので人を選びますが、とりあえず文字が好きだという人にはおすすめできると思いました。
作者円城塔の考えた独特の文字世界でその奇想、そのふざけっぷりを大いに楽しむべき本といえるでしょう。
短編「文字渦」

本書に掲載されている最初の作品が表題作「文字渦(モジカ)」です。
秦の始皇帝(姓名は嬴政)の求めに応じて、俑という職人が兵馬俑(ヘイバヨウ)をつくる場面を描写した作品です。(私の好きな時代の話です。やったー!)
兵馬俑は古代中国でお墓に副葬される兵士や馬などの人形のことです。

兵馬俑
上の画像を見てみるとわかりますが、秦代の兵馬俑ってものすごく写実的ですよね。
だから、俑は嬴政をかたどった兵馬俑を作るにあたって、しっかりと本人の姿を目に焼き付けてから、粘土に向かいます。
ところが嬴政の印象はなんともとらえどころがなく、見るたびにくるくると変わっていってしまう。
この嬴政の姿のとらえどころのなさを、円城塔はどのように表現したのでしょうか。
どれもが同じ嬴であったが、目を凝らせばどれもが異なる嬴だった。『文字渦』p.25
なんと、嬴政というワードが文章に登場するたびに、「嬴」の字の「女」の部分を別の字にコロコロと置き換えることで、見るたびに別人のように印象が変わることを表現したのです。
漢字自体に意味を持たせるのではなく、似た漢字を代わる代わる登場させることで嬴政のとらえどころのなさを表現するという試みですね。漢字そのものの概念を覆すかのようなこの発想がすごい。
私などは最初、これが演出であることに気づかず、「あっ、誤字があるぞ。もう、しょうがないなぁ(笑)」などと思っていた不届き者ですからね(←バカ)
その直後、これが誤字ではなく「演出」であることに気づき、この作品の恐ろしさを思い知ったという次第です。(ちなみに、あとの編で「誤字」自体をテーマにした短編があります。本作ほど、本来的な意味での誤字脱字が許されない作品もありませんね・・・!校正の人、大変だっただろうなー(笑))
まさに、小説だからこそできる演出ですよね~!斬新!!
読む側も、この最初の1編「文字渦」を読むことで、「ほほう!これはこういう前衛的な作品か!」とある種の心構えができてくるわけです。
いやー。よくできてますねえ。
ところでこの本、感想がとても書きづらいのです。
どういうことかといいますと、本文中で使われている漢字が変換できないんですよ!
「読み方がわからなくて変換できないの?ぷぷぷ(笑)」とかではなくて、本当にその字が変換候補に存在しないんです。
本当なら、「嬴」の字がどういう風にコロコロ変わったのかを書いていきたいのですが、変換できないから書けない。これはなかなかくやしいですが、ぜひ本書を手に取ってこの字の作り込みを味わってほしいですね!
これだけでもおもしろい趣向ですが、本作にとってはこれはまだまだ序の口。
第2編目以降も、手を変え品を変え、奇抜な発想で読者を驚かせてくれます。いやースゴイ本ですね。
スポンサーリンク
文字が光ったり、闘ったり
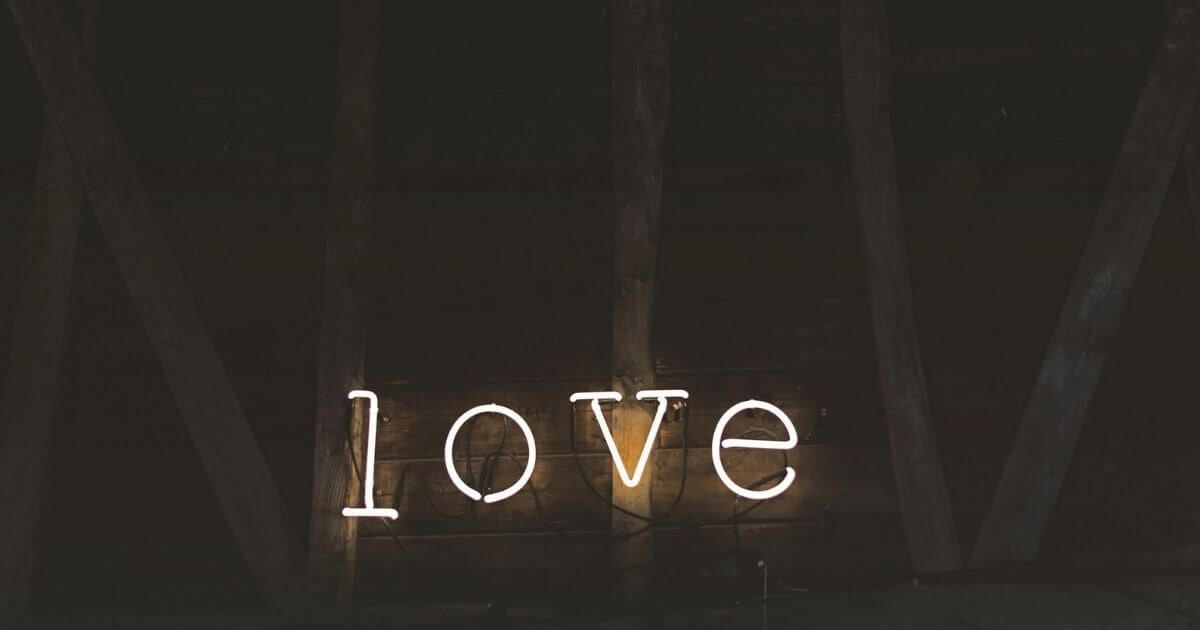
嬴政の「嬴」の字が少しずつ変形していく1編目の短編「文字渦」。
変わった趣向で文字自体のおもしろさを提供してくれる短編となっていますが、2編目「緑字」は1編目とはうってかわって理系的な要素に満ちた作品となっています。
大部分が無機質な英数字の海で構成されるテキストファイルのなかに、わずかに存在する「日本語のテキストでできた島々」。その日本語テキストのなかに「光る文字」に関する記述が発見されます。
――文字の発する光は、それ自体による発行と、受けた光の周波数を変調して発光し直す蛍光に分類される。文字自体による発光は、文字同士の複雑な相互作用によって生み出されるものであり、反応には比較的多くの文字を必要とする。『文字渦』p.34
文字自体に光を発する機能なんてないのですから、いってみればこれは作家円城塔のでっち上げ、大法螺の類なわけです。
本作は終始この文章のような調子で、読者に対して大胆不敵なまでに堂々と大法螺を吹いてきます。
また、この大法螺がよくできているんですよね~!
読み進めていくうちに、次第に信じてしまいそうになります。本当はこういうことだったんじゃないかと。
最終的には「ほうほう、なるほど」とかつぶやいてしまう。(←バカ)
文系チックな話を展開しているなと思ったら、思いっきり理系側に反転したりと、読者の脳をかき回し、振り回ししながらあの手この手で読者を撹乱させてきます。
この脳味噌を疲弊させてくるかのような怒涛のでっち上げ、大法螺が本作『文字渦』の大きな特徴といえるでしょう。非常に疲れてしまいますが、この上なくおもしろい読書体験です。
部首を多重に装備可能な型も存在しており、「尹」字は人偏を装備して「伊」字に、さらに口偏を加えて「咿」字へと変形することでも知られる。『文字渦』p.34
これは第3編目の「闘字」からの抜粋です。
いきなり何を言い出すんだという感じですが、もうなんかいかにもそれっぽいことをさも当然のようにサラサラと言っています。
文字同士を闘わせるという文化を一通り説明したあと、文字が部首を装備するというくだりに差し掛かったところです。
真面目な仮面を被りながら思いっ切りふざけに徹する馬鹿馬鹿しさがおもしろさに転化している場面ですね。
サラッと「変形することでも知られる」と言っていますが、知らねえよ(笑)
このシュールな笑いにだんだんとハマっていくんですよ。この本を読んでいると!
本作に収録されている12編はいずれも終始こんな感じの馬鹿馬鹿しさにあふれています。いや、すげえな。
取っつきづらいものも

最初の1編「文字渦」は秦の始皇帝嬴政が登場し、思いっきり歴史小説の世界観で話が進みます。
と、思いきや、2編目「緑字」は1編目とはうってかわってデータベースやフォント、プリンターの細かい理系的な、情報処理的な用語がバンバン出てきます。
作者の円城塔さんはもともとウェブエンジニアだったそうで、このあたりの情報処理系に強いのかもしれませんね。
この文系的とも理系的とも言いづらい、ストーリーの振れ幅の大きさは、本作の大きな魅力であると同時に、本作特有の読みづらさ、取っつきづらさに繋がっています。
簡単に言ってしまえば、読みやすい短編と読みづらい短編があるということです。
私は典型的な、生まれながらの、正真正銘の文系人間ですので、物語が理系に振れる短編に差し掛かると、とたんに読書スピードが落ちました(笑) だって変な数式が出てきたりするんだもん!
それでも、オチというか、作者が狙ったおもしろさは理解できるように配慮されていますので、難しいなと思った箇所は流し読みでもいいんじゃないかなと思います。
※電子書籍ストアebookjapanへ移動します
【ネタバレ感想】すでに読了した方へ
危険!ネタバレあり!本作に登場する「名言」を少しだけ紹介してみましょう。
終わりに
クセが強く、読む人を選ぶと思いますが、個人的には非常に楽しい本でした。
ただ、この本の魅力はブログではその全てを語れないなとも思いましたね。
なにしろ変換できない部分に魅力がありすぎるんですよ!
本ブログを読んで、少しでも興味を持っていただけましたらぜひ本作を手に取って、そのブログで「変換できなかった部分」も楽しんでもらいたいですね~!
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
つみれ
スポンサーリンク

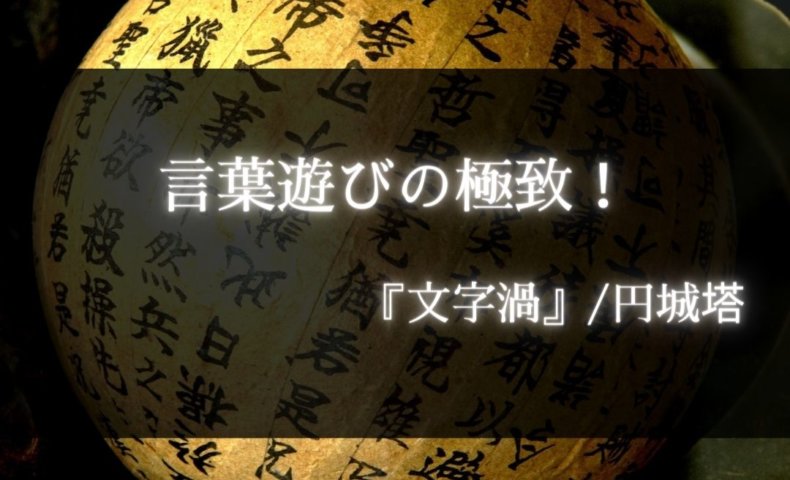



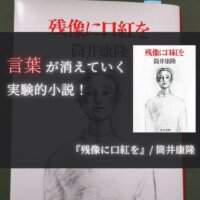
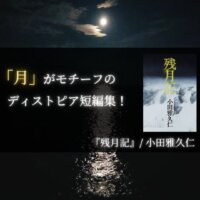


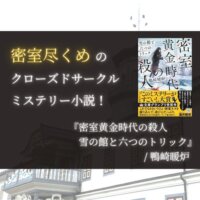
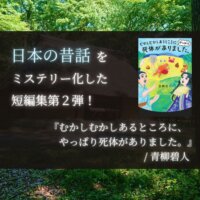
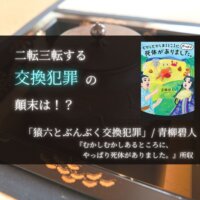
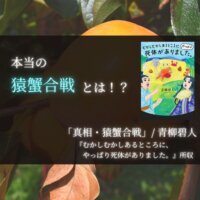
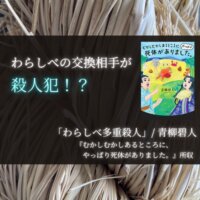
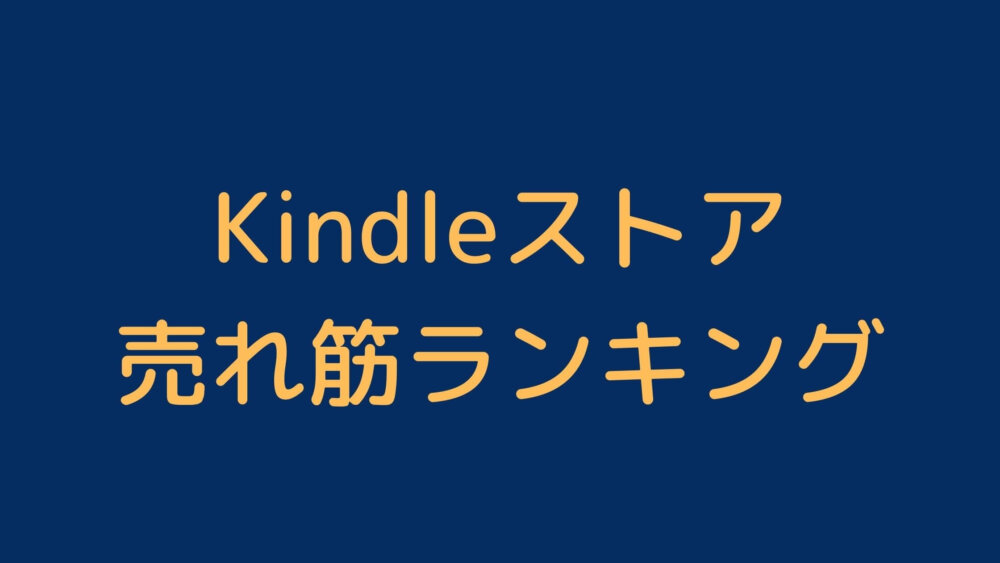
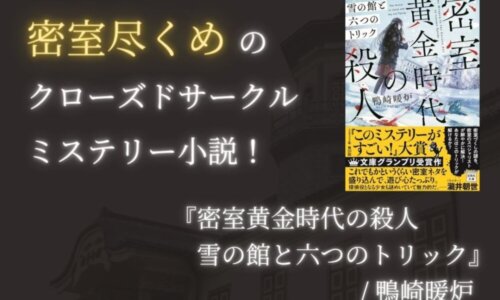
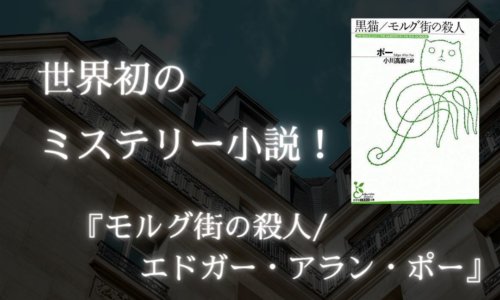

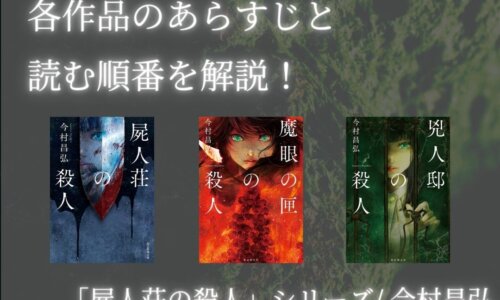
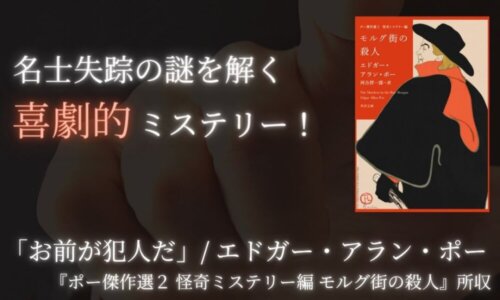
この記事へのコメントはありません。