世界から言葉が消えていく『残像に口紅を』p.8
本を開くと、冒頭にこんな一文が掲げられています。
この小説では、少しずつ言葉が消えていくのです。
「えっ!?」と思いますでしょ?
例えば、「あ」という言葉が消えれば、「愛」も「あなた」も使えなくなる。
章が進むたびに、どんどん言葉が失われていく。
そんな驚くべき試みを実際にやってしまった実験的な小説があるんです。
それが今回感想を書いていく筒井康隆さんの『残像に口紅を』です。
アメトーーク!の「読書芸人」企画でカズレーザーさんに紹介され、話題になりました。
ストーリーがどうこうだからおもしろいとかそういう小説ではありませんが、使える文字が少しずつ減っていくという趣向そのものを楽しむ作品といっていいでしょう。
ちょっとだけネタバレ感想は折りたたんでありますので、未読の場合は開かないようご注意ください。
作品情報
書名:残像に口紅を (中公文庫)
著者:筒井康隆
出版:中央公論新社 (1995/4/18)
頁数:236ページ
スポンサーリンク
目次
言葉が消えていく実験的小説
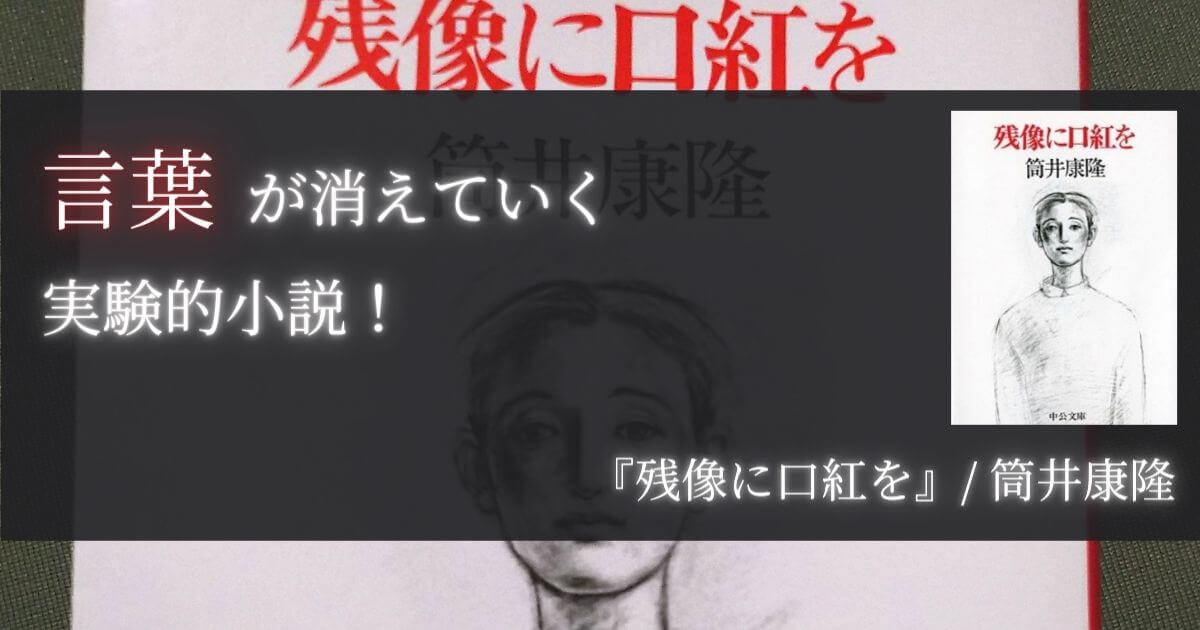
私が読んだ動機
「アメトーーク!」で紹介されているのを観て気になっていたところに、書店で見つけたので購入しました。
こんな人におすすめ
- 話題の小説が読みたい
- 実験的な試みが好き
- 言葉が消えていくというオンリーワンの楽しさを味わいたい
これはすごい一冊です。もう本当におどろきました。
1章進むたびに「音」が一つずつ消えていくんです。
どういうことかといいますと、事項以下で説明していきましょう。
少しずつ音が消えていく

例として、「あ」が消えた場合、この小説ではその後二度と「あ」という音を持つ言葉は登場しません。
この小説では最初の章で「あ」が失われてしまいます。従って、作品中に「あ」という音は一回も登場しないということになります。
当然、「あなた」という言葉が使えなくなりますので、他の言葉、「きみ」などで代用するしかなくなるわけです。
「あなた」を「きみ」に変えても大意は変わりませんが、日本語の持つ微妙なニュアンスが伝わらなくなります。
章が進むごとに使える音が減っていき、後半になればなるほど、より大げさで不自然な代用をすることになります。
このことから生まれる微妙な意味合いのズレや、苦労してその場に相応しい言葉を探しているであろう筆者の言語センスを楽しむ。
後半になればなるほど、使える言葉の制約が厳しくなっていく。
そんな趣向の小説となります。なんという素晴らしい発想なのでしょうか。
これ、思いついたとしても実際には書かないと思うんですよね。
終盤のストーリーを想像するだけで、破綻が目に見えていますものね。
『残像に口紅を』のすごいところは、ある程度、物語としての体裁を保ったまま、結局すべての音が消えるところまで完走しているというところです。
序盤はきちんとした文章なのですが、使える音が制限されてくるとだんだんと言葉遣いが荒くなり、やがては片言じみていく。
それでも物語は続いていくのです。
まさに奇才の作品というしかありません。
スポンサーリンク
消えた音を名前に持つ存在も消える

音がだんだんと消えていくという発想だけでもすごいのですが、もう一つおもしろい要素が付加されています。
それは「消えた音を名前に持つものはその存在自体が消える」というものです。
例えば、「い」という音が消えたとします。
すると、犬という動物自体の存在が小説から消えるのです。
それも、その時点から急に消えたという形ではなく、人間の意識が「もとから犬という動物は存在しなかった」という形に改変されてしまいます。
このギミックが、物語に切なさやもの悲しさ、諧謔やおかしみといった独特の味わいを付加する要素となっています。
物語が進むうちに、登場人物たちも「存在が消える」というこの不思議な現象に気づいてきます。
そうすると、「自分が消えてしまうまえにこの旨そうな料理を食べてしまわなければ!」と意気込んだ瞬間に料理が消えるといったような、この小説ならではのおかしみが生まれてくるのです。
記憶の消え方

犬が消えたとして、その瞬間から犬の記憶がきれいさっぱり消えるわけではありません。
記憶が完全に抹消されるまで、わずかばかりの猶予があるのです。
急速に犬に対する記憶が薄れていくなか、登場人物の犬に対する最後の感傷が描かれる。
この要素が数々の名シーン、珍シーンを生んでいるんですよ。
主人公の家族、とりわけ3人の娘たちは、物語の序盤で狙い撃ちされたかのように順番に消えていきます。
娘が消えた瞬間、主人公が浸る最後の感傷。これがなかなかにドラマチックです。
※電子書籍ストアebookjapanへ移動します
【ちょっとだけネタバレ感想】すでに読了した方へ
危険!ネタバレあり!本作に登場する「名言」を紹介しながら、本作について語ってみる。
終わりに
この小説を読んで、ストーリーがうんぬんかんぬんと言ってしまうのは野暮というものです。
だんだんと音が消えていく実験的な小説。この発明的な発想こそを楽しむべき作品といっていいでしょう。
すばらしい作品だと思います。
私としては、使える音が10を切ったあとの、詩的でリズミカルで音楽的な世界をぜひとも味わってほしい。
そんな小説でございました。おもしろかった!
最後まで読んでくださり、ありがとうございます。
つみれ
スポンサーリンク

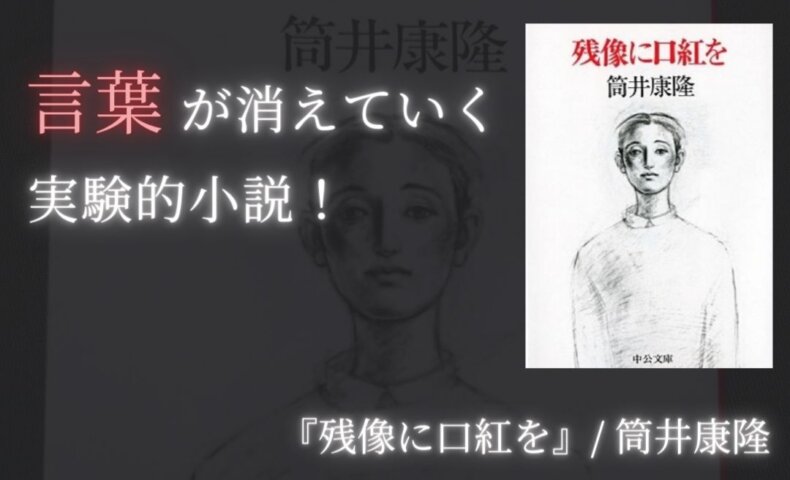


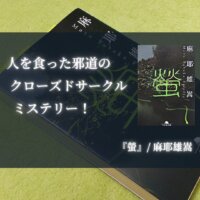











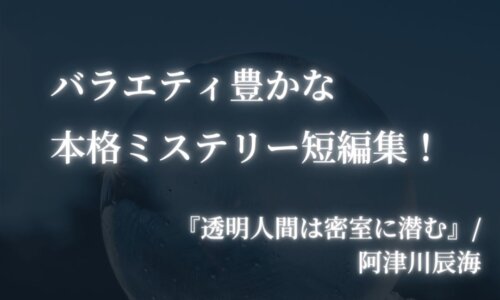
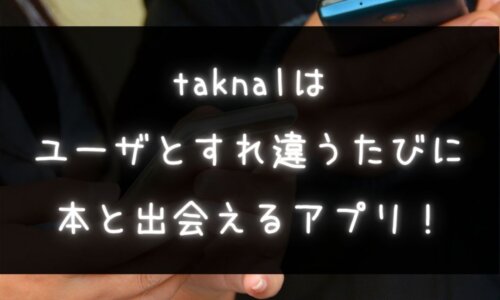


この記事へのコメントはありません。